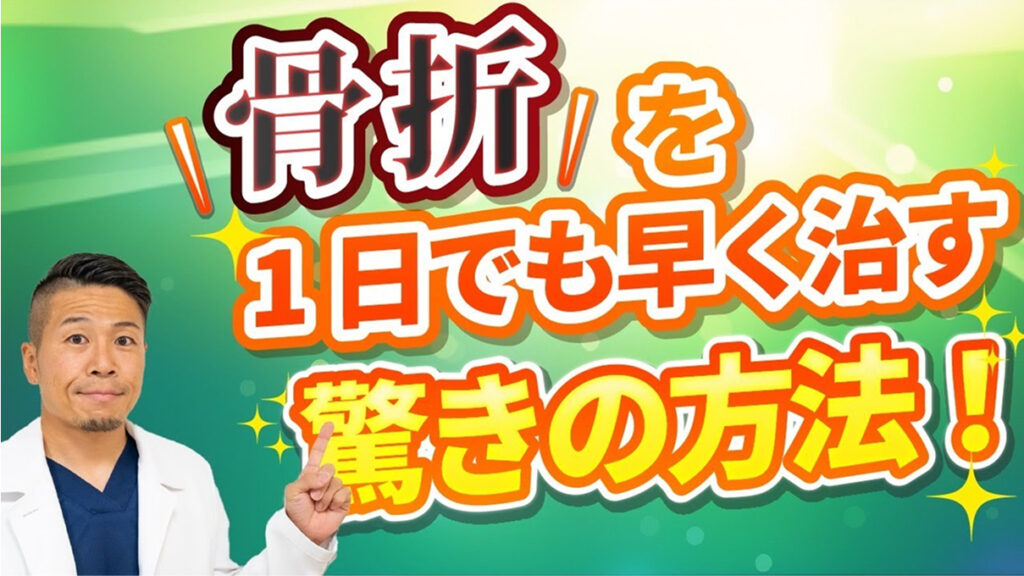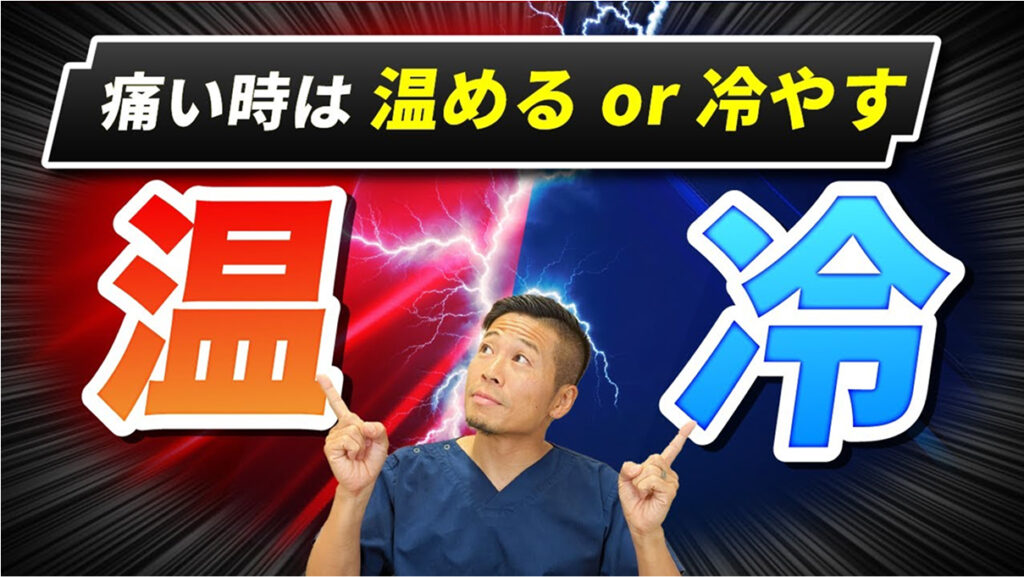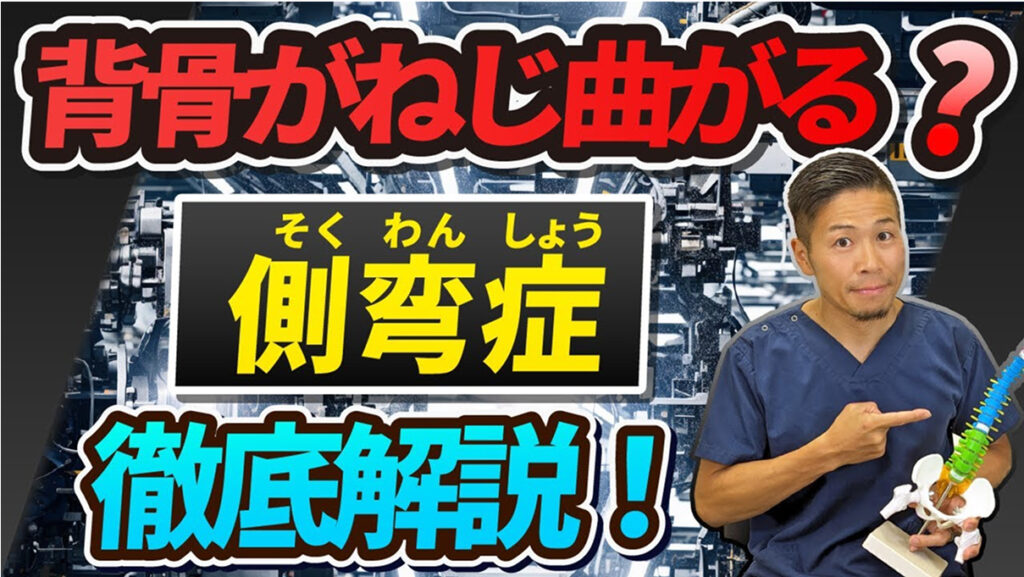猫背・巻き肩の原因と対策とは?整形外科医が教える、たった2つの意識で変わる姿勢改善術
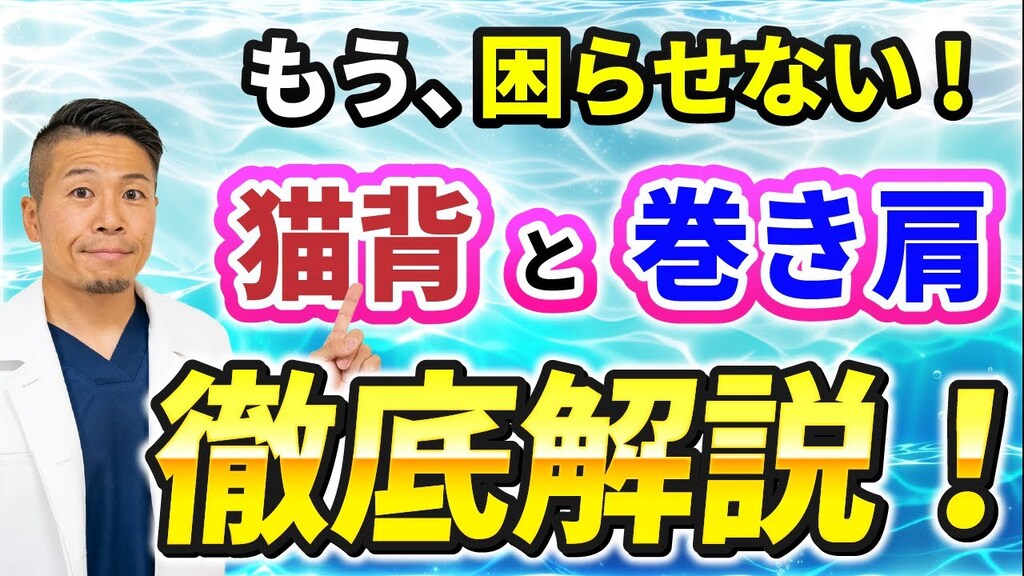
肩こりがつらいから肩を揉む、姿勢の悪さが気になるから無理に胸を張る。そんなその場しのぎの対策を繰り返してはいませんか?実は、多くの人が悩む猫背や巻き肩は、肩や背中だけを意識しても根本的には解決しません。整形外科医によると、その本当の原因は体の土台である「骨盤の傾き」にあることが多いのです。
この記事では、混同されがちな猫背と巻き肩の明確な違いから、骨盤に着目した本質的な原因、そして日常生活で簡単に実践できる医学的に正しい改善方法までを分かりやすく解説します。

猫背と巻き肩の違いとは?まずはセルフチェックでタイプを知ろう
猫背と巻き肩は、見た目が似ているため同じものとして扱われがちですが、医学的には全く別の状態を指します。姿勢を正しく改善するためには、まず自分の体の状態を正確に把握することが大切です。ここでは、それぞれの特徴と関係性について詳しく見ていきましょう。自分の姿勢がどちらのタイプに当てはまるか、あるいは両方なのかを意識することが、改善への重要な第一歩となります。
猫背:背骨、特に胸の骨(胸椎)が丸くなる状態
人間の背骨は、本来なだらかなS字カーブを描いています。首(頸椎)と腰(腰椎)は前に、胸(胸椎)は後ろに湾曲しているのが正常な状態です。猫背とは、このうち胸の部分である胸椎が、正常な範囲を超えて過度に丸まってしまっている状態を指します。横から見たときに、背中全体がCの字のように丸く見え、頭が体よりも前に突き出てしまうのが特徴です。主に背骨そのもののカーブの問題であり、壁に背中をつけて立った時に、後頭部が自然につかない場合は猫背の可能性が考えられます。
巻き肩:肩の位置が体の中心より前に出ている状態
巻き肩は、背骨のカーブとは直接関係なく、肩関節そのものの位置の問題を指します。横から見たときに、耳の穴からまっすぐ下におろした線よりも、肩の中心が前に出てしまっている状態が巻き肩です。背筋は伸びていて猫背ではないのに、デスクワークなどで腕を前に出す姿勢が続くことで、肩だけが内側に巻いてしまうケースも少なくありません。肩甲骨が外側に広がり、胸の筋肉が縮こまってしまうことが原因で起こります。仰向けに寝たときに、肩が床から浮いてしまう方は巻き肩の傾向があります。
猫背と巻き肩の関係性|併発するがイコールではない
猫背になると、背中が丸まることで構造的に肩甲骨が前に押し出され、結果として巻き肩を併発することが非常に多くあります。このため、猫背と巻き肩はセットで語られることが多いのです。しかし、先述の通り、猫背ではない巻き肩も存在します。つまり、猫背の人は高い確率で巻き肩でもありますが、巻き肩の人が必ずしも猫背であるとは限りません。この違いを理解しないと、巻き肩なのに背中を伸ばす運動ばかりするなど、的外れなケアをしてしまう可能性があります。
猫背・巻き肩の本当の原因は「骨盤の傾き」にあった
スマートフォンや長時間のデスクワークが姿勢を悪くすると言われますが、それらはあくまできっかけに過ぎません。整形外科医が指摘する根本的な原因、それは体の土台である骨盤の傾きです。特に座っている時間が長い現代人は、無意識のうちに骨盤が後ろに傾いて(後傾して)しまいがちです。骨盤が後ろに倒れると、その上に乗っている背骨はバランスを取るために全体的に丸くなり、結果として猫背を引き起こします。多くの人が姿勢を治そうと肩や背中を意識しますが、土台である骨盤が傾いたままでは、上半身だけで良い姿勢を保つのは非常に困難です。まず見直すべきは肩や背中ではなく、すべての基本となる骨盤の位置なのです。
猫背・巻き肩が引き起こす悪影響|肩こりから精神不調まで
姿勢の悪さは、見た目の印象や肩こりだけの問題ではありません。自分では気づきにくい体の内側や、精神面にまで深刻な影響を及ぼすことがあります。ここでは、猫背や巻き肩を放置することで起こりうる、代表的な3つの不調について解説します。
呼吸が浅くなり、自律神経が乱れる
背中が丸まると、胸郭と呼ばれる肺を覆う骨格が圧迫されて動きが制限されます。これにより、肺が十分に膨らむことができず、一回一回の呼吸が浅くなってしまいます。呼吸が浅い状態が続くと、体は酸素不足になり、疲れやすさやだるさを感じやすくなります。さらに、浅い呼吸は体を緊張状態にする交感神経を優位にさせがちです。その結果、リラックスできずに眠りが浅くなったり、イライラしやすくなったりと、自律神経のバランスの乱れにつながることもあります。
消化不良や胃の不快感を引き起こす
猫背の姿勢は、常にお腹を圧迫している状態です。この圧迫によって腹圧が高まり、胃や腸といった消化器官の正常な働きが妨げられてしまいます。食後に胃がもたれたり、消化不良を起こしやすくなったりするのは、このためです。食べ物がスムーズに消化されないだけでなく、胃酸が食道へ逆流しやすくなるため、胸やけや逆流性食道炎のリスクも高まります。原因不明の胃腸の不調が、実は姿勢の悪さから来ていたというケースは少なくありません。
ネガティブな思考に陥りやすい精神的な影響
人の心と体は密接につながっています。例えば、気分が落ち込んだ時には、自然と視線が下がり、背中が丸まってしまう経験は誰にでもあるでしょう。これとは逆に、姿勢が心に影響を与えることも分かっています。うつむき加減で背中が丸まった姿勢をとり続けると、無意識のうちに気分まで沈み込み、ネガティブな思考に陥りやすくなると言われています。姿勢を正すことは、体の健康だけでなく、心を前向きに保つ上でも非常に重要なのです。

猫背・巻き肩の治し方|整形外科医が教える根本改善2ステップ
ここまで解説した根本原因を踏まえ、整形外科医が推奨する本質的な改善法をご紹介します。これは、つらい筋トレや複雑なストレッチではありません。日常生活の中で少し意識を変えるだけで、誰でも実践できる非常にシンプルな2つのステップです。この意識を習慣づけることで、体は本来あるべき正しい位置を思い出していきます。
ステップ1:すべての基本「骨盤を立てる」意識を持つ
まず最も重要なのが、体の土台である骨盤を正しい位置に保つことです。これを骨盤を立てると言います。特に座っている時に意識してみましょう。椅子に深く腰掛け、お尻の下にある二つの硬い骨、坐骨に均等に体重が乗るのを感じてください。骨盤が後ろに寝てしまったり、前に倒れすぎたりせず、地面に対して垂直に立つイメージです。この骨盤が立った状態が、正しい背骨のS字カーブを作るためのすべての基本となります。まずはこの感覚を体に覚えさせましょう。
ステップ2:自然と胸が開く「肋骨の一番下を前に出す」
骨盤を立てる意識ができたら、次のステップに移ります。ここでやりがちなのが、無理に胸を張ったり、肩甲骨をぐっと寄せたりすることですが、これはかえって体を緊張させてしまいます。意識すべきは、肋骨の一番下の部分です。骨盤を立てた状態をキープしたまま、みぞおちの少し下にある肋骨の一番下の縁を、ほんの少しだけ前にスライドさせるようなイメージを持ってみてください。これにより、丸まっていた胸椎が自然と伸び、肩の力も抜けて正しい位置に収まります。
猫背・巻き肩は「骨盤を立てる」意識から改善しよう
今回は、混同されがちな猫背と巻き肩の明確な違いから、その根本原因である骨盤の傾き、そして具体的な改善方法までを解説しました。多くの人が悩む姿勢の問題は、肩や背中といった表面的な部分にアプローチするだけでは解決しません。体の土台である骨盤を立て、その上に背骨が自然なS字カーブを描けるように意識することが、最も重要で効果的なのです。今回ご紹介した2つのステップは、特別な時間や場所を必要としません。日々の生活の中で少しずつ意識を向けることで、あなたの体は必ず変わっていきます。正しい姿勢で、不調知らずの健やかな毎日を目指しましょう。