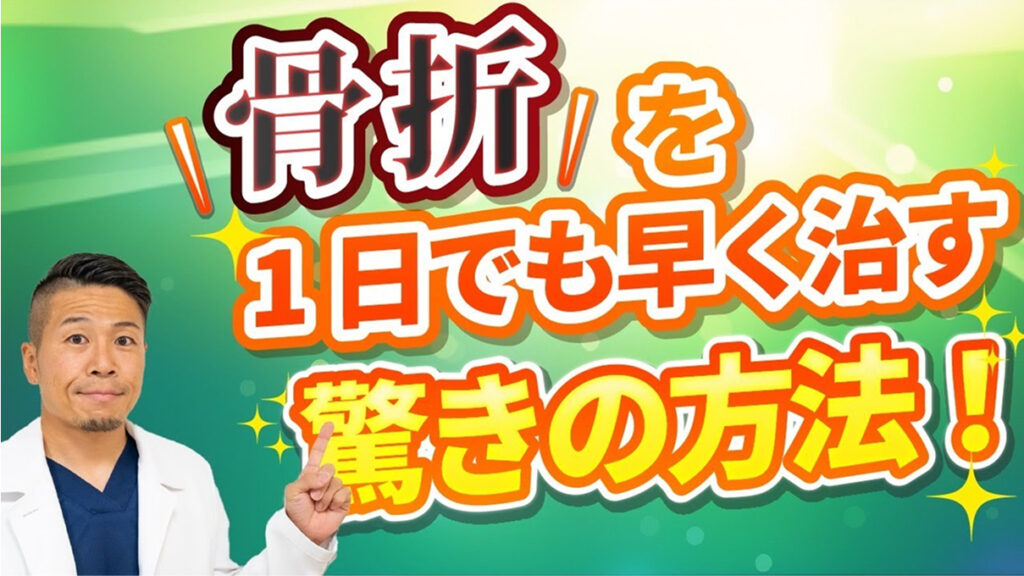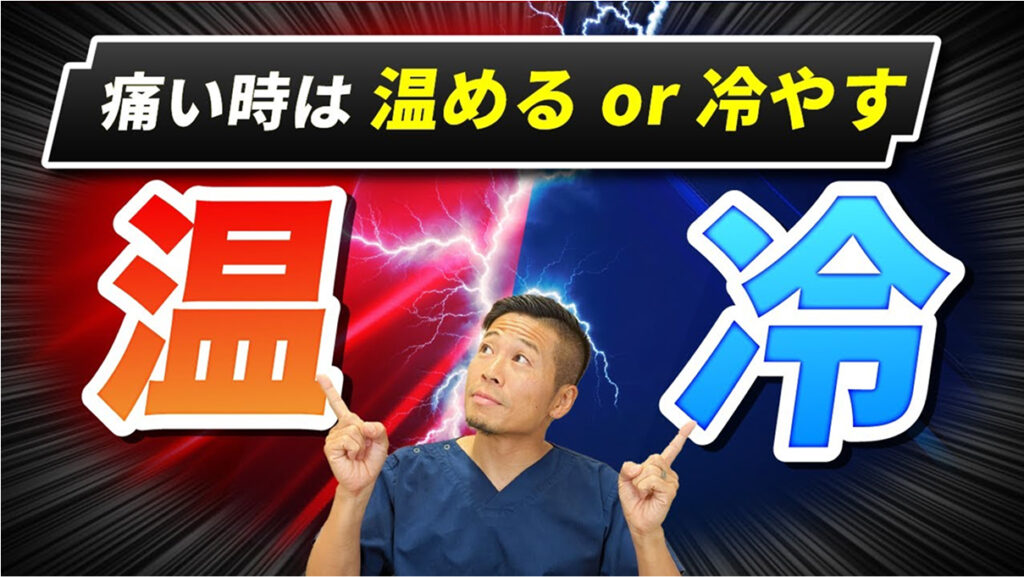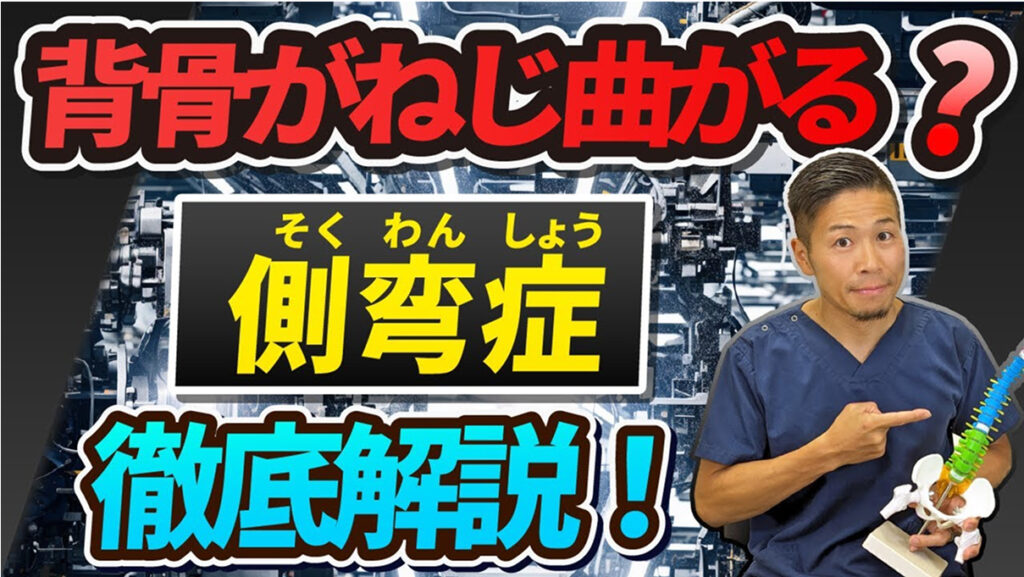下の血圧だけ高いのはなぜ?医師が教える年齢別の原因と対処法
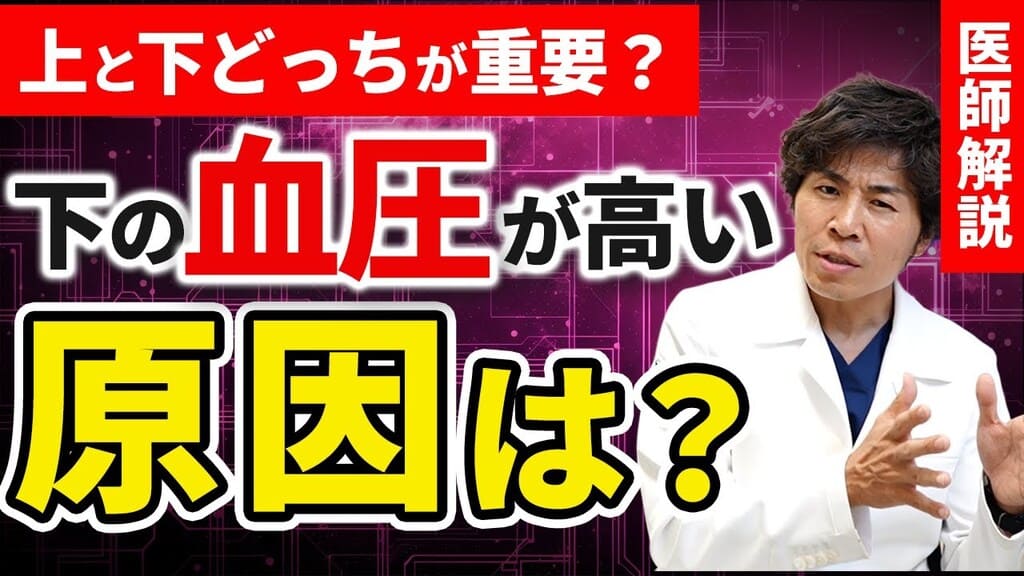
「上の血圧は正常なのに、下だけが高い」と言われた経験はありませんか?実はこの状態は「孤立性拡張期高血圧」と呼ばれ、若い世代ほど注意が必要なサインです。下の血圧は、心臓が休んでいる間も血管にかかる圧力を示しており、常に血管が緊張状態にあることを意味します。放置すると、将来の心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まる可能性も。
この記事では、下の血圧が高くなる原因や隠れた病気との関係、年齢別に注目すべき血圧の違い、そして今日から始められる生活改善法を医師の知見をもとに分かりやすく解説します。

下の血圧が高い状態とは?上との違いを医師が解説
血圧には「上」と「下」がありますが、それぞれが示す意味を理解していない人も多いでしょう。実は、この2つの数字は心臓と血管の働きを表す大切なサインです。
血圧の「上」と「下」は何を示しているのか
血圧の「上」は、心臓が収縮して血液を全身に送り出すときの最大圧力で、「収縮期血圧」と呼ばれます。心臓のポンプ力を示す指標です。一方で「下」は、心臓が一時的に休んでいる間にも血液を送り続ける圧力で、「拡張期血圧」と呼ばれます。これは大動脈や血管の弾力によって生まれる圧力であり、血管がしなやかで健康であれば適正範囲に保たれます。つまり、上の血圧が心臓の働きを示すのに対し、下の血圧は血管の健康状態を反映しているのです。両方のバランスが取れていることが、循環器系の安定につながります。
孤立性拡張期高血圧とは
上の血圧が正常なのに下だけが高い状態は、「孤立性拡張期高血圧」と呼ばれます。これは、心臓が休んでいる時間でさえ血管が常に高い圧力にさらされていることを意味します。若年層や中年層で特に多く見られる傾向があり、血管が硬くなっているわけではなく、末梢血管が収縮して血液が流れにくくなっている場合が多いです。この状態を放置すると、血管へのダメージが蓄積し、将来的に動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中といった重大な疾患のリスクが高まります。見た目の数値がわずかな上昇でも、体の中では静かな異変が進行していることがあるため、早めの対応が大切です。

なぜ下の血圧だけが高くなるのか
上の血圧が正常でも、下の血圧だけが高くなる背景には、血管や生活習慣、さらには隠れた病気が関係しています。それぞれの原因を理解することで、正しい対策が見えてきます。
末梢血管抵抗が増えるメカニズム
下の血圧を押し上げる最大の要因は「末梢血管抵抗」の増大です。これは、手足の先などにある細い血管が硬くなったり、収縮して血液の流れが悪くなることで生じます。水道のホースを指でつまむと勢いが増すのと同じ原理で、血液が流れにくくなると圧力が高まるのです。若い世代では大動脈の弾力が保たれているため上の血圧は上がりにくい一方、細い血管の抵抗が高まることで下の血圧だけが上昇するケースが多く見られます。これが「孤立性拡張期高血圧」の特徴です。長期間放置すると、血管内壁が傷つきやすくなり、動脈硬化の初期段階へと進行するリスクが高まります。
生活習慣による影響(塩分・運動不足・ストレス)
日常生活の中にも、下の血圧を上げる要因が潜んでいます。まず、塩分の多い食事は体内の水分量を増やし、血液量が増加するため血圧が上昇します。さらに、運動不足は血管の柔軟性を低下させ、血流を悪くする原因となります。精神的ストレスも見逃せません。ストレスによって交感神経が活発化し、血管を収縮させるホルモンが分泌されることで、血圧が上がるのです。アルコールや喫煙も同様に、血管を収縮させる作用を持ち、長期的に下の血圧を押し上げます。生活習慣が重なることで、血管に慢性的な負担がかかり、知らないうちに下の血圧が高い状態が続いてしまうのです。
隠れた病気が原因のケース(睡眠時無呼吸・腎疾患など)
生活習慣を見直しても下の血圧が下がらない場合、隠れた病気が関係している可能性があります。代表的なのが「睡眠時無呼吸症候群」です。睡眠中に呼吸が止まり、体が酸素不足になると交感神経が興奮して血管を収縮させ、夜間でも高血圧状態が続きます。この状態が慢性化すると、日中の下の血圧も高くなります。また、腎臓病や甲状腺機能低下症などの内分泌疾患も血圧を上昇させる要因になります。特に薬を飲んでも血圧が下がりにくい場合は「二次性高血圧」が疑われます。症状が軽くても、専門医による検査を受けることで早期発見につながります。
年齢によって違う「注目すべき血圧」
血圧の重要度は年齢によって変わります。若い人ほど「下の血圧」に注意が必要であり、高齢になると「上の血圧」が健康状態をより正確に示す指標となります。
50歳未満では「下の血圧」に注目すべき理由
50歳未満の世代では、上の血圧よりも下の血圧が将来の心血管疾患リスクを予測する重要なサインとされています。若い人の高血圧の多くは、心臓よりも末梢の細い血管に問題があることが多く、これが下の血圧の上昇として現れます。つまり、血管のしなやかさが失われ始めている初期段階を示しているのです。この時期に放置すると、血管の内壁にストレスがかかり続け、数年後には動脈硬化が進行してしまう恐れがあります。しかし、生活習慣を改善することで血管機能は回復する可能性が高い点も特徴です。下の血圧の上昇は「警告」でもあり「チャンス」でもあるのです。
60歳以上では「上の血圧」が重要になる背景
60歳を超えると、体内の血管構造そのものが変化していきます。加齢とともに大動脈の弾力が低下し、血液を送り出す際の圧力が上がるため、上の血圧(収縮期血圧)が高くなる傾向にあります。一方、下の血圧(拡張期血圧)は逆に低下しやすく、血管の硬化が進むことで血流の戻りが弱くなるのです。そのため、この年代では「上の血圧」がより健康リスクを反映する指標となります。下の血圧が低くても安心せず、全体のバランスを重視することが大切です。高齢層では、過度に下げすぎることがかえって脳や腎臓の血流低下を招く場合もあるため、医師の管理のもとで適切な数値を維持することが求められます。
下の血圧が高いときの正しい対処法
下の血圧が高いと指摘されたとき、まず取り組むべきは生活習慣の見直しです。薬に頼る前に、日々の食事・運動・体重管理などを整えることが改善の第一歩になります。
塩分制限とカリウム摂取
塩分の摂りすぎは、体内の水分量を増やし、血液量を増加させて血圧を上昇させます。1日の塩分摂取量は6g未満が目安とされ、加工食品や外食に含まれる“隠れ塩分”にも注意が必要です。さらに、カリウムを多く含む野菜や果物(バナナ、ほうれん草、アボカドなど)を摂ることで、体内のナトリウム排出を促進し、血圧のコントロールがしやすくなります。また、食事の際に「出汁や香辛料」で味を整える工夫をすれば、無理なく減塩を継続できます。栄養バランスを意識し、外食より自炊を増やすことも有効です。
運動と体重管理
血圧を下げるには、運動による血管の柔軟性改善が欠かせません。特にウォーキングやサイクリングといった有酸素運動は効果的で、1日30分、週に180分以上が目安です。運動を習慣化することで血流が改善し、末梢血管の抵抗が自然と下がっていきます。さらに、体重を1kg減らすと血圧が約1mmHg下がるといわれており、減量は非常に効果的です。極端なダイエットではなく、毎日の食事量と活動量のバランスを整えることが重要です。継続できるペースを意識して、生活の中に自然に運動を取り入れましょう。
薬に頼る前に見直すべき生活習慣
薬を服用する前に、まず徹底すべきなのが生活習慣の修正です。十分な睡眠、ストレスの軽減、禁煙、節酒などが血圧改善の基本になります。睡眠不足や強いストレスは交感神経を刺激し、血管収縮を引き起こすため、どんなに食事や運動を頑張っても効果が半減します。また、アルコールやタバコは一時的なリラックス効果に見えても、長期的には血管の弾力を失わせる原因となります。薬が必要になる前に、まずはこれらの生活改善を3〜6か月続けてみることが勧められます。
血圧測定と医師への相談
自分の血圧を正しく把握することは、最も基本でありながら軽視されがちな習慣です。特に下の血圧は日中のストレスや睡眠の質に影響されやすく、病院だけでなく家庭でも定期的に測定することが大切です。朝と夜の2回、同じ時間帯・同じ条件で測ると変化が分かりやすくなります。家庭血圧の記録を続けることで、医師がより正確な判断を下しやすくなり、必要に応じて薬物療法への切り替えもスムーズに行えます。「測る・記録する・相談する」の3ステップを習慣化することが、将来の血管トラブルを防ぐ最善策となります。
まとめ
下の血圧が高いというのは、血管が常に緊張しているサインです。特に若い世代では、末梢血管の抵抗が高まっている初期の変化として現れ、放置すれば動脈硬化のリスクを高める要因になります。原因の多くは生活習慣にあり、塩分の摂りすぎ、運動不足、ストレス、そして隠れた病気が関係します。まずは毎日の血圧測定から自分の体を知り、食事・運動・睡眠の質を整えることが大切です。生活を見直すことで血圧は徐々に安定し、将来の心臓や脳の病気を防ぐことができます。下の血圧の上昇は、危険の前触れであると同時に、体からの生活を変えるチャンスと捉えてください。